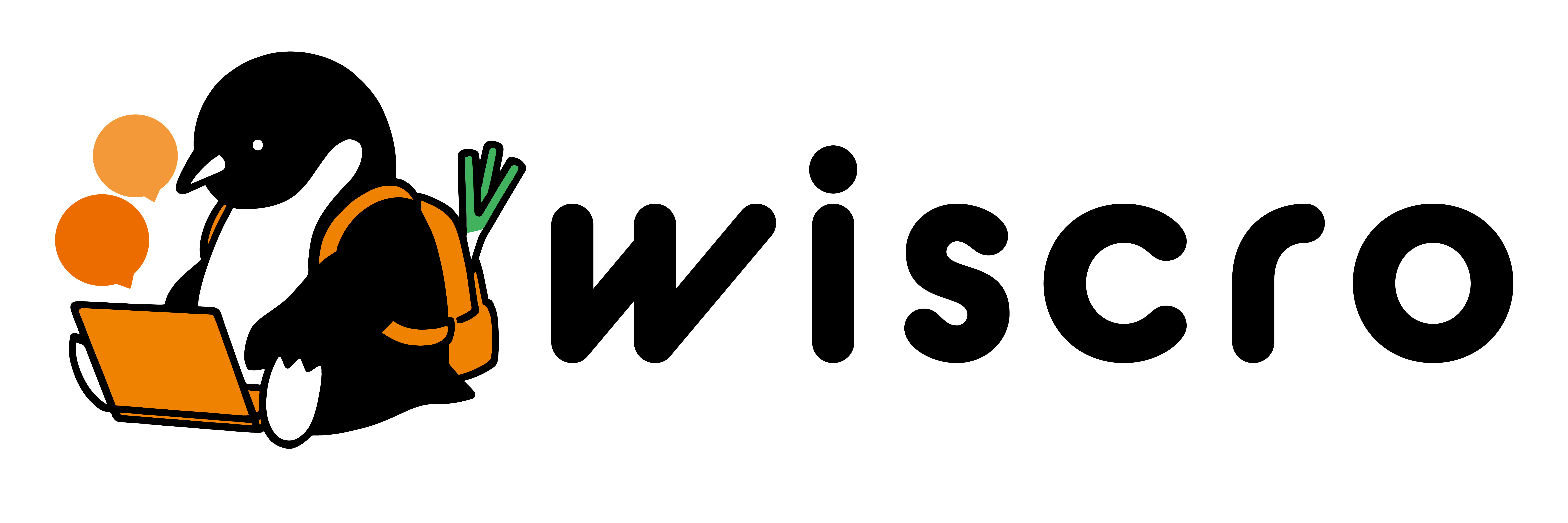採用面接で聞いてはいけない質問とは?HR担当者必見のリスク回避ガイド
採用面接で何気なく聞いた質問が法律違反になってしまった...そんな事例が年々増加しています。
厚生労働省の調査によると、令和5年度だけで745件の指導事例があり、多くが「雰囲気を和らげるつもりの質問」から始まっています。
今回は、日本の採用面接における法的リスクを分かりやすく解説し、実践的な対策をご紹介します。
絶対に聞いてはいけない14の禁止事項
厚生労働省が定める「就職差別につながるおそれがある14事項」は、職業安定法に基づき厳格に禁止されています。違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰の対象となる可能性があります。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地
- 家族の職業・続柄・健康・収入
- 住宅状況(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣施設)
- 生活環境・家庭環境
本来自由であるべき事項
- 宗教、支持政党
- 人生観・生活信条、尊敬する人物
- 思想、労働組合・社会運動
- 購読新聞・雑誌・愛読書
特に注意が必要なのは、男女雇用機会均等法により禁止されている性別に基づく質問です。「結婚の予定はありますか?」「出産後も働く予定ですか?」といった質問は、たとえ相手が同意していても法的に問題となります。
実際にあった違反事例
大阪労働局の指導事例から、軽微に見える発言でも問題となったケースをご紹介します。
性別差別発言の例
- 「女性を採用してもいいけど、すぐに辞めるでしょう」
- 「男性ばかりの職場に女性一人で大丈夫?」
家族情報の違法収集
- 面接前のアンケートで「家族構成」「兄弟の人数・学年」を記入させる
これらは全て、面接官が「悪意なく」行った質問や発言でしたが、法的な指導対象となっています。
適切な質問とは?判断基準を理解
判断基準は「職務遂行に必要な適性・能力との関連性」 です。
聞いても良い質問の例
- 「これまでの職歴で最も実績を残したことは何ですか?」
- 「困難に直面して乗り越えた経験を具体的に教えてください」
- 「あなたの強みを、当社の業務でどのように活かせますか?」
- 「5年後・10年後にどのような姿になっていたいですか?」
これらの質問は、業務に直結する能力や意欲を確認するもので、法的に問題ありません。
効果的なリスク回避策
1. 構造化面接の導入
最も効果的な対策は構造化面接の導入です。事前に決められた質問項目、統一された進行方法、明確な評価基準を設けることで、面接官による評価のばらつきを防ぎ、公正な選考を実現できます。
2. 面接官の研修強化
定期的な研修により、禁止事項の理解を深め、適切な質問技法を身につけることが重要です。特に新任の面接官には、法的リスクについて十分な教育を行いましょう。
3. 複数面接官制度
一人の主観に頼らず、複数の面接官による相互チェック機能を設けることで、不適切な質問や評価を防げます。
2023年以降の新たな注意点
近年の採用環境の変化により、新たなリスクも生まれています。
オンライン面接の普及により、候補者のプライベート空間が見えてしまい、意図せず家庭環境を判断材料にしてしまう危険があります。2023年データでは、大企業・中堅企業の6割超がオンライン面接を導入しており、適切なガイドラインの整備が急務です。
AI選考の拡大も新たな課題です。2024年卒採用でAI選考導入企業が31%に達しており、アルゴリズムによる意図しない差別を避けるため、AI活用における公平性の確保が重要になっています。
まとめ:優秀な人材確保と法的リスク回避の両立
採用面接における法的リスクは年々厳格化していますが、適切な知識と対策により十分に回避可能です。重要なのは「職務遂行に必要な適性・能力」という明確な基準に基づいて質問を組み立てることです。
構造化面接の導入、継続的な面接官研修、組織的なリスク管理体制の構築により、優秀な人材の確保と法的リスクの最小化を両立できます。変化する法制度や社会情勢に適応し、定期的にガイドラインを見直すことが、持続可能な採用活動の鍵となります。
関連資料